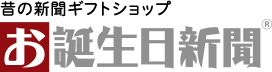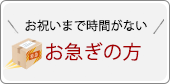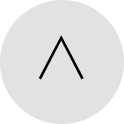大切な人の退職はどう祝うべき?知っておきたい退職祝いの由来や風習
[contentblock id=20]
退職祝いの由来
退職祝いは慶事のひとつですが、結婚祝いや出産祝い、長寿祝いなどのほかのお祝い事と比べると、なんとなく特殊なイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
なぜなら、会社を辞めることになった経緯はそれぞれ理由があり、必ずしも「退職=めでたいこと」とはいえない場合もあるためです。
会社や個人それぞれの考え方によっても異なりますが、退職をお祝いするのは主に、定年退職、結婚による退職(寿退社)、出産による退職、栄転・昇進による退職の場合です。
退職祝いには、長年働いてきた労をねぎらう意味のほか、退職後の新たな人生への門出を祝福する意味が込められています。
退職祝いの風習~家族の場合~

長寿祝いなどの場合、多くはめでたい日を迎えることを親戚やご本人に近しい人たちなどにもお知らせして、大々的なお祝いを行います。
一方で、退職祝いの場合は、退職することを周りの人たちに知らせるといった意味合いはなく、内輪で済ませることがほとんどです。
家族で祝う場合はこれといった決まりごとはありませんが、プレゼントを贈ってこれまで家族のために働いてくれたことへの感謝の気持ちを表したり、自宅やお店で食事会を開いたり、旅行を計画するご家庭が多いようです。
退職祝いの風習~職場関係の人の場合~

職場関係の方へ向けた退職祝いの場合は、部や課の単位で送別会を開き、退職される方を送り出すのが一般的です。
規模が小さな会社の場合は、社内全体で行う場合もあります。
またこのとき、職場内でお祝いの品を用意することも多くあります。
会社によっては歓送迎会を行わない慣例があるところもありますが、その場合も、何かしらの贈り物をする場合が多いようです。
お祝いの品の選び方に関しては、いくつかしきたりや習わしといえるものがあります。
定年退職

定年退職の場合、贈る相手は目上の方であることがほとんどでしょう。
そのため、勤勉に働きなさいという意味にもとれる文房具やカバン、腕時計などは、ふさわしくないとされています。
これまでの労をねぎらう退職祝いの品という意味でも、避けた方が無難かもしれません。
また、人を踏みつける意味にもとれる履物・敷物もタブーとされています。
最近では気にされることは少なくなってきましたが、基本的に目上の方には、現金や金券を贈らないという慣例もあります。
なるべく贈答品として“物”を用意するのがベストです。
結婚・出産による退職

寿退社のお祝いの品は、結婚祝いと同様、縁が切れる・壊れるといった意味合いから、刃物や割れ物は避けた方がよいとされています。
とはいえ、夫婦で使えるペアの食器類などは喜ばれることも多いですので、ある程度柔軟に考えてかまいません。
また、出産による退職の場合は、万が一のことがあったときに辛い思いをさせないための配慮として、出産前にはベビー用品は選ばないのが通例です。
退職時には別のものを贈り、無事出産されてから、出産祝いとしてベビー用品を贈るのもよいでしょう。
栄転・昇進による退職

栄転や昇進の場合は今後も仕事を続けていくことが決まっているので、文房具や腕時計といったビジネスで役立つものを贈ることは珍しくありません。
ただ、年齢が上になればなるほどはしきたりや風習を気にされる方も少なくないので、目上の方に贈る場合には、相手のことをよく考えて選びましょう。
日本では昔から、何かをもらったらお返しをする習慣があり、特にお祝い事の際には基本的に、“もらいっぱなし”ということはありません。
しかし退職祝いの場合は、長寿祝い同様、お返しはしなくてよいという考え方が一般的です。
とはいえ、会社でお返しをする慣例があれば、基本的にはそれに従います。
お祝い事のお返しは「半返し」と呼ばれ、もらった品物の半分くらいの金額で用意するのがならわしですので参考にしてみてください。
[contentblock id=20]