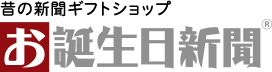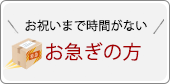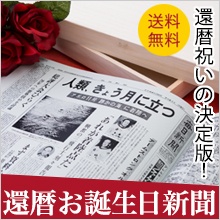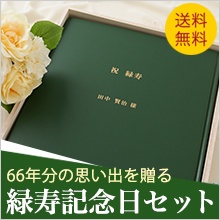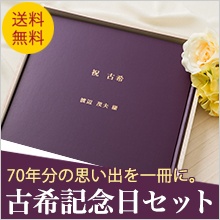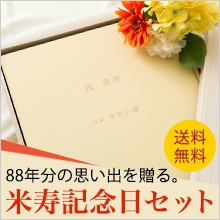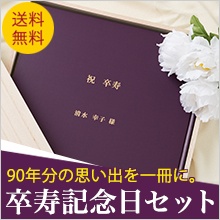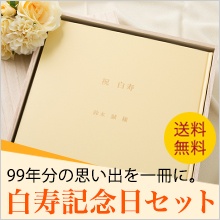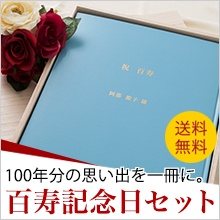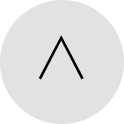長寿祝いのお返しは必要?
基本的には、「家族に対しては必要ないけれど、友人・知人、職場関係の人などに対してはお返しをする」と考えておくとよいでしょう。
もともと、数え年で年齢を数えていた昔は、お正月に家族で集まって長寿祝いをすることが一般的だったため、お返しをする習慣はありませんでした。
しかし近年では、普段は顔を合わせることが少ない親戚や友人・知人、職場関係の方なども呼んで盛大な長寿祝いをすることも多く、結婚祝いや出産祝いなど他のお祝い事と同じように、お返しをすることが増えています。
[contentblock id=10]
お返しにはどのようなものを贈る?
お祝い事のお返しは、「半返し」が基本といわれており、いただいた贈り物の半額の物をお返しとして贈ります。
もちろん、きっちり半額でなければならないという決まり事ではないため、あくまでも予算の目安として考えましょう。
長寿祝いのお返しの品としては、紅白まんじゅうや紅白餅などは定番といえます。
和菓子やお餅が苦手な方には、洋菓子の詰め合わせなどもおすすめです。
また、甘い物が苦手な方には、ツルや亀などの縁起がよい物をあしらった細工かまぼこなどを贈ることもできます。
お返しを贈る相手のことをよく知らない場合、好みが分かれる食べ物は避けたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、タオルや風呂敷、ふくさ、お箸、茶器などの食器類などであれば、日常でも使えますし、記念として長く形に残ります。
ちなみに、お祝い事のお返しのことを「内祝い」ということがありますが、お返しと内祝いは厳密には違います。

お返しとは、贈ってもらった人にお礼の気持ちとして贈り物をすること、内祝いとは、幸福を近しい人たちと分け合うために贈り物をすることです。
そのため内祝いの場合は、贈り物をもらっていない近所の人たちなどにも贈ることがあります。
長寿祝いの中でも特に大々的に行うことが多いのは、還暦や米寿です。
地域によっては、ご近所の人や親戚などに、還暦の際は年齢を記した風呂敷を、米寿の際はものさしや餅、升掻き棒(お米を升で量る際に、盛り上がった表面を平らにならすための道具)を贈る風習があります。
お住まいの地域の風習に合わせて、お返しや内祝いの品を選んでみても良いのではないでしょうか。