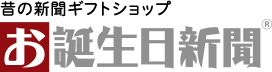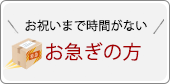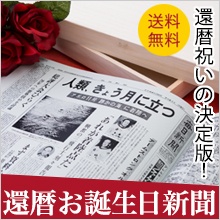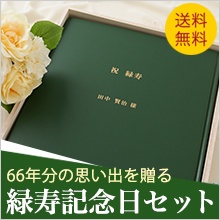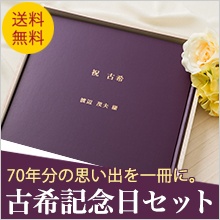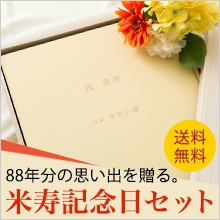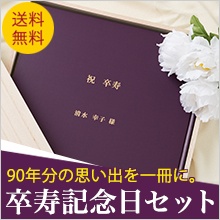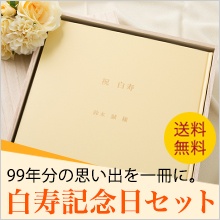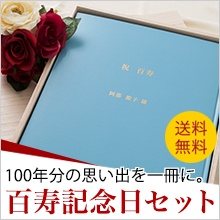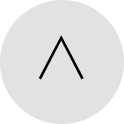長寿祝いの熨斗に関するマナーをご紹介
[contentblock id=1]
熨斗(のし)とは?

「熨斗(のし)」は、もとは細く切ったアワビを薄く削ぎ、伸ばして乾かしたものを色紙で包んだ、飾り物のことを指します。
薄く伸ばした“のしアワビ”を用いることが、その名前の由来となっています。
アワビは古来より不老不死の妙薬として信じられており、婚礼や式典などの祝い事や出陣の際に行われた「三献の儀」には、勝ち栗、昆布と並ぶ肴として欠かせない縁起物でした。
また、さまざまな贈り物の中でも最高級品だと考えられており、後に礼を尽くす意味で、贈答品や進物に添えられるようになったことが、現在にも伝わっています。
今では印刷技術の発達により、のしは掛け紙の右肩に印刷されるようになり、しきたりは簡略化されています。
そのため一般的には、のし紙やのし袋のことを“のし”と呼んでいます。
長寿祝いの熨斗に関するマナー
内のしと外のし
のしには、贈り物に直接のし紙をかけてその上から包装を施す「内のし」と、贈り物を包装した後にのし紙をかける「外のし」があります。
礼儀としてのしを付けること自体が重要であるため、どちらにすべきといった決まりごとはありません。
郵送などで手渡しできない場合はのしに傷がつかないよう内のしに、直接ご本人に渡す場合は表書きが見えるよう外のしに、といったように、状況によって使い分けるとよいでしょう。
また、贈る相手と親密な間柄であるならば、形式にこだわらず、リボンやラッピングをかけて贈っても問題ありません。
ただし、のし紙をかける場合は、リボンは用いないようにしましょう。
水引
古くは、品物に掛け紙をし、「水引」という紐でくくって贈り物をしていました。現在では、水引ものしと同じく、のし紙に印刷されています。
水引は、その結び方に大きな意味があります。
長寿祝いには、簡単に解けて何度でも結び直せることから、繰り返し祝い事があるようにとの願いを込めて、「蝶結び(花結び)」を用います。また水引の色は、めでたいことを表す紅白や金赤、金銀などが最適です。
表書き
古くは品物と一緒に目録をつけていましたが、現在は簡略化されたことによってその風習がなくなり、代わりに表書きを記します。
表書きは「御祝」や「祝○○(還暦、喜寿などお祝いの名前)」などとし、下段には表書きよりも一回り小さな字で贈る相手の名前を書きます。毛筆や筆ペンを使用し、楷書で丁寧に記しましょう。