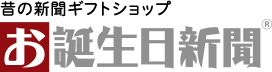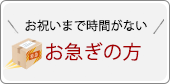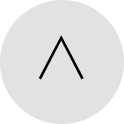日本人の平均寿命はこうして移り変わった!~日本の長寿祝いの歴史~
厚生労働省が調査し、2018年7月20日に発表した「平成29年簡易生命表」によると、2017年の日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳であることがわかりました。
これは男女ともに過去最高の数字であり、男性の平均寿命は5年連続で80歳超えを記録しています。
世界的に見ると、トップは男女ともに香港であるものの、日本は男性3位、女性2位と上位につけていて、まさに長寿大国といえるでしょう。
しかし、日本人の平均寿命はいつからこんなに長くなったのでしょうか?
今回は、日本人の昔と今の平均寿命を比較するとともに、還暦や古希など、さまざまな長寿祝いの歴史を振り返ります。

[contentblock id=9]
目 次
日本人の平均寿命の変化
日本人の平均寿命の移り変わりを時代別に紹介します。

平均寿命50歳超えは平成に入ってから
日本人の平均寿命は平成に入ってから、格段に伸びたようです。
かつて「人生50年」だったことは有名ですが、実際に平均寿命が50歳を超えるようになったのは第二次世界大戦後の1950年前後以降であることがわかっています。
昭和でも太平洋戦争中の1941~1945年における日本人の平均寿命は31歳であり、明治・大正時代よりも低かったようです。
江戸時代の平均寿命は幅が広い

明治・大正時代の平均寿命は44歳とはっきりした数字が出ていますが、江戸時代の平均寿命は32~44歳とかなりあいまいです。
この理由として、江戸時代における記録の残し方が挙げられます。
全体的な人数はある程度把握できているものの、きちんとした戸籍制度がなかったため、生まれた子どもの数が知られていないということも多かったようです。
そのため、調査方法によって平均寿命にばらつきが出てしまったと考えられます。
人骨で平均寿命を割り出した時代も
江戸時代以前にさかのぼると安土桃山時代の平均寿命は30代、室町時代は15歳、鎌倉時代が24歳、平安時代は30歳、飛鳥・奈良時代が28~33歳、古墳・弥生時代が10~20代、そして縄文・旧石器時代が15歳前後であることがわかっています。
しかし、江戸時代以前になると記録がさらに少なくなり、現在に比べるとかなり不確かな数字といえるでしょう。
縄文時代や室町時代は人骨の推定死亡年齢から平均寿命を割り出していますし、平安時代の寿命は貴族だけで割り出しています。
過去の平均寿命はかなり不確かではありますが、それでも平成に入ってからの日本人の長寿化は目を見張るものがあるでしょう。
代表的な長寿祝い一覧

前章で紹介した通り、平成以前は平均寿命が今の半分ほどしかなく、長生きは大変おめでたいこととされていました。
長寿者をお祝いする「長寿祝い」の風習もかなり古くから存在していたようです。
次の章ではそれぞれの長寿祝いの歴史を紹介しますが、その前に代表的庵長寿祝いの種類を確認しておきましょう。
| 還暦(かんれき) | 60歳の長寿祝い |
| 緑寿(ろくじゅ) | 66歳の長寿祝い |
| 古希(こき) | 70歳の長寿祝い |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳の長寿祝い |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳の長寿祝い |
| 半寿・盤寿(はんじゅ・ばんじゅ) | 81歳の長寿祝い |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳の長寿祝い |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳の長寿祝い |
| 珍寿(ちんじゅ) | 95歳の長寿祝い |
| 白寿(ひゃくじゅ) | 99歳の長寿祝い |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 100歳の長寿祝い |
有名なのは還暦から百寿までですが、それ以降も108歳の茶寿(ちゃじゅ) 、110歳の珍寿(ちんじゅ) 、111歳の皇寿(こうじゅ) 、119歳の頑寿(かんじゅ)、そして120歳の大還暦(だいかんれき)と続きます。
それぞれの長寿祝いの歴史
「長寿祝い」の誕生から、現在までの流れを見ていきましょう。

長寿祝いの起源は中国
「長寿祝い」の概念は中国から伝えられたと言われています。
紀元前550年頃存在した思想家・孔子が説いた儒教では、敬老思想や長寿を尊ぶことがよしとされています。
「吾、十有五にして学に志、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知り、六十にして耳順、七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」という、有名な言葉を一度は聞いたことがあるでしょう。
この言葉は日本にも伝わり、奈良から平安時代にかけては40歳(四十賀)、50歳(五十賀)、60歳(六十賀)をそれぞれ長寿の年として、貴族の間でお祝いする風習が生まれました。
この頃は唐末から宋代の流行にならって、詩を贈ることで長寿を祝う風習があったとされています。
70歳以降の長寿祝いが生まれた平安時代
しかし、鎌倉時代以降は四十賀や五十賀という考えは薄れ、かわって古希や喜寿などより長命の長寿祝いが誕生したことで、呼び方も現在のものに変わってきました。
まだまだ平均寿命が短いこの時代に、なぜ70歳以降の長寿祝いが生まれたのでしょうか?
その答えは107歳まで生きた平清盛のひ孫・藤原貞子の存在が大きいとされています。
天皇一族である藤原貞子の長寿祝いをしないわけにはいかず、新しい長寿祝いとして古希や喜寿が設定されたという説が有力です。
古希・喜寿・米寿・白寿のテーマカラーが紫色であるのは、当時高貴な身分の人しか着られなかった紫色の衣装を藤原貞子が着ていたためと言われています。
ちなみに77歳の喜寿や88歳の米寿祝いが生まれたのもこの頃です。
長寿祝い発祥の中国では昔から「ぞろ目」を不吉な数字と捉えていて、この年にはお祝いすることで厄払いをしようと考えていました。
余談ですが、ひな祭り(3月3日)や端午の節句(5月5日)もこの思想によって生まれたとされています。
還暦・傘寿・半寿・卒寿が生まれた江戸時代

長寿祝いといえば還暦祝いを思い浮かべる人が多いようですが、意外にも還暦祝いが生まれたのは江戸時代と比較的最近です。
干支が60年で一周し、61年目から新しいサイクルに入るため、「暦が還る」という意味で「還暦」と名付けられました。
他の長寿祝いは数え年で行うのに、還暦祝いは満年齢60歳でお祝いするのはそのためです。
さらに江戸時代には傘寿、半寿、卒寿など、長寿祝いのバリエーションが増えていきました。
戦はなくても、火事や伝染病など死が常に隣り合わせの存在だった江戸時代では、長命をありがたいと感じる意識が高かったために生まれたのではと推測されています。
長寿祝いの最後の誕生は2002年

ここまでで紹介してきた通り、大変歴史の長い長寿祝いですが、ごく最近生まれたものもあります。
それは、2002年に日本百貨店協会に提唱された「緑寿」です。満年齢65歳で行う緑寿は年金受給開始の年であり、退職する人が増えるため、長寿祝いで労いと感謝を伝えることができます。
今後も日本の平均寿命や長寿祝いの考え方に変化が訪れれば、さらに新しい長寿祝いが誕生するのかもしれません。
最後に
日本の長寿祝いはもともと中国から伝わったものですが、さまざまな事情によって日本独自の変化を遂げてきたことがわかりました。
還暦や傘寿、卒寿など江戸時代には日本オリジナルの長寿祝いが生まれ、平成に入ってからも緑寿が生まれています。
それらの名前の由来が、「百から一引くと白=99歳のお祝いは白寿」「米という字を分解すると八十八になる=88歳のお祝いは米寿」など、日本ならではの言葉遊びが興味深いところです。
昔の人が長寿祝いに込めていた想いや歴史を理解することで、より心のこもった長寿祝いを開くことができるでしょう。
[contentblock id=10]